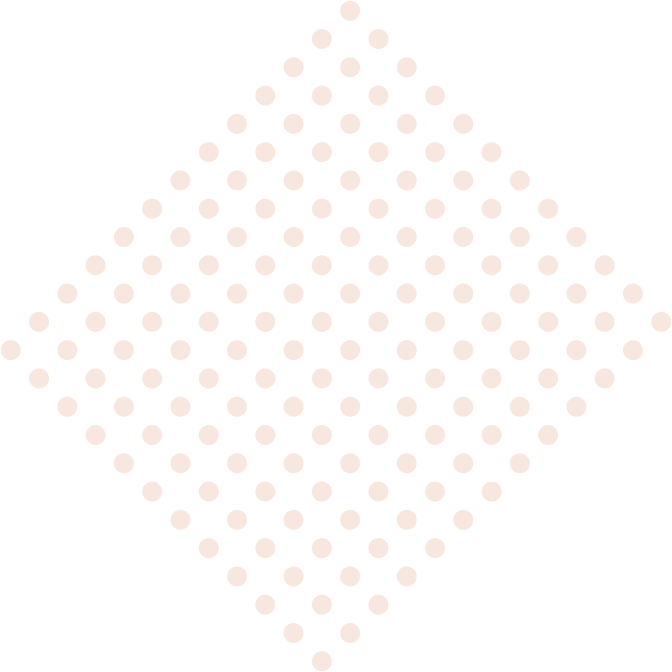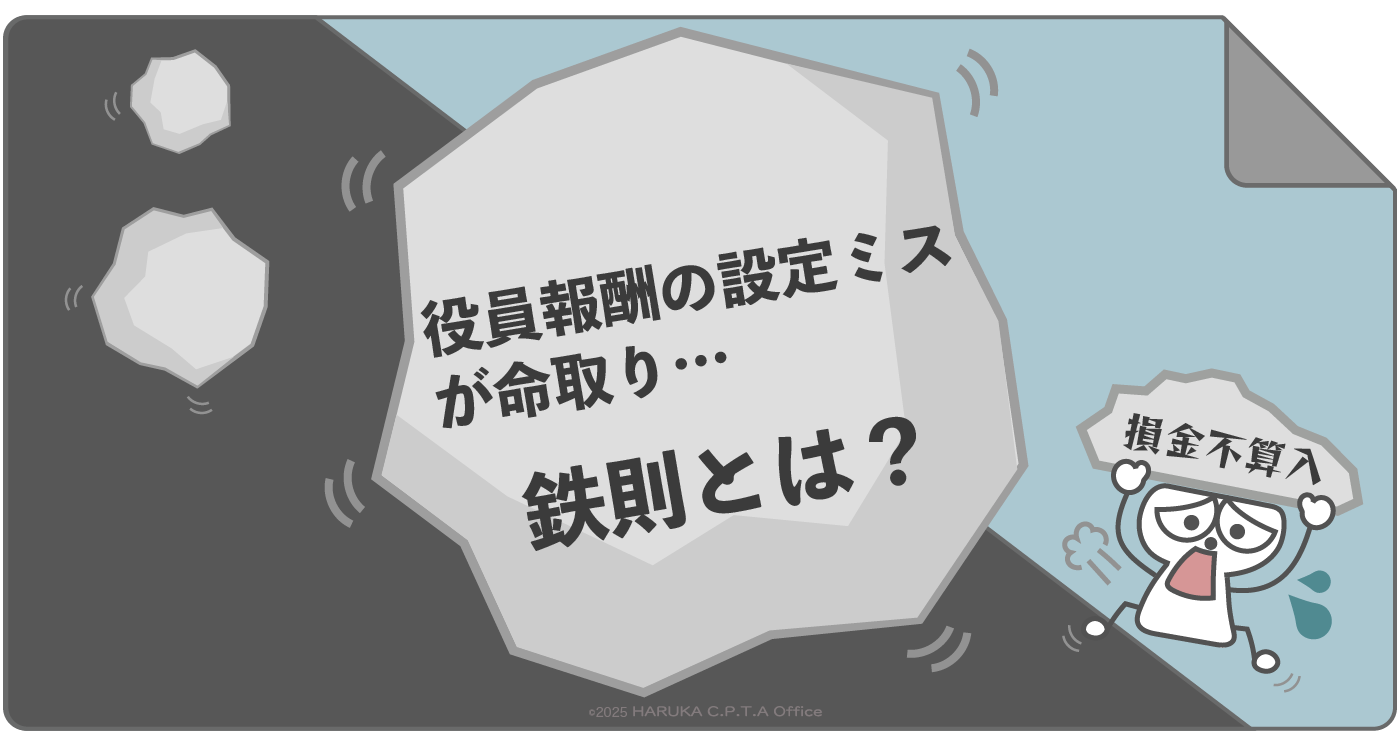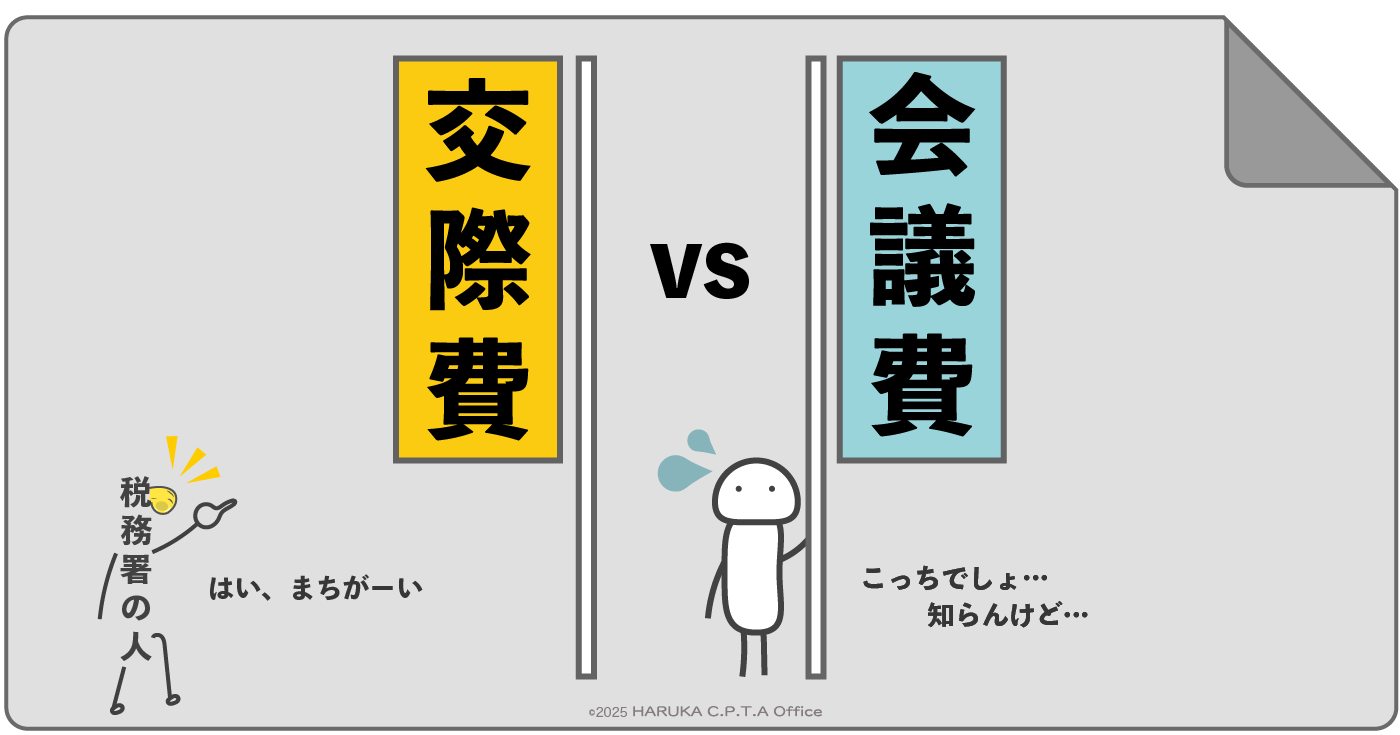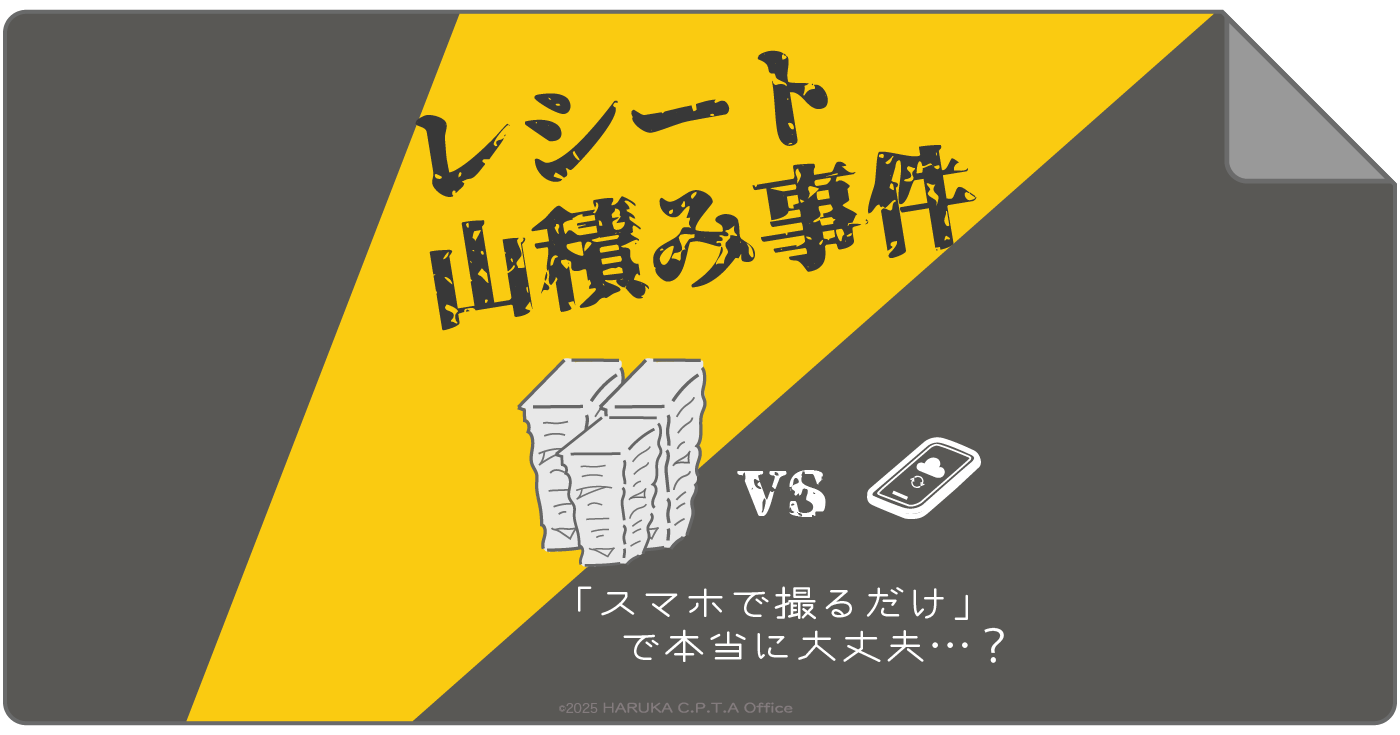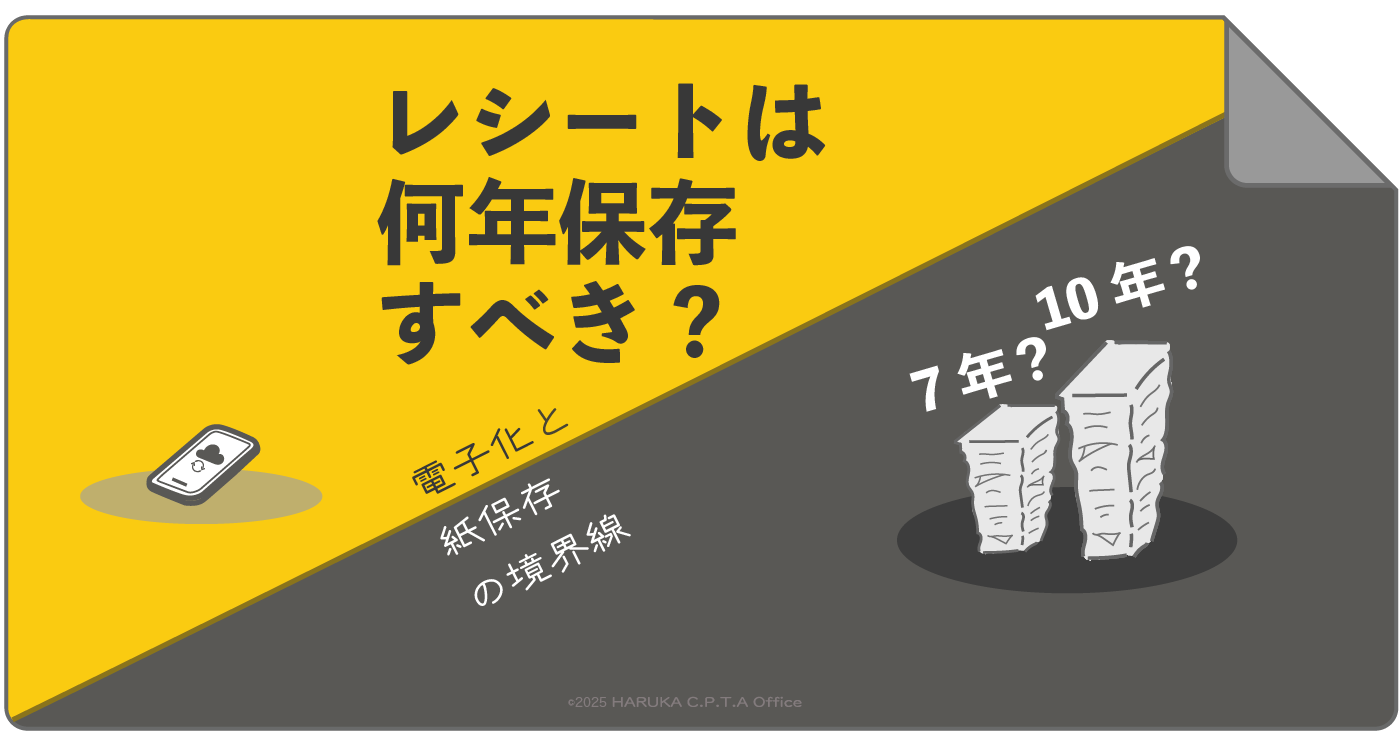こんな悩みを解決
-
役員報酬を途中で変更しても大丈夫か不安
-
税務署から損金算入を否認されないか心配
-
節税と資金繰りを両立する適正な報酬額を決めたい
結論
役員報酬は「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」のいずれかでなければ損金に算入できない。特に中小法人で採用されるのは定期同額給与であり、期首から3か月以内に決定し、原則として毎月同額で支給しなければならない。設定ミスや途中変更は損金不算入となり、法人税負担や資金繰りに大きな悪影響を及ぼす。
制度のポイント整理
損金算入できる役員給与の3類型
-
定期同額給与
→ 原則毎月同額を継続支給。期首から3か月以内に確定する必要あり。 -
事前確定届出給与
→ 賞与的な支給だが、支給時期・金額を事前に届出することで損金算入可。 -
利益連動給与
→ 上場企業など一部法人限定。中小法人は対象外。
損金不算入となる典型例
-
期首から4か月目以降に報酬額を変更した
-
業績悪化を理由に一時的に減額した
-
増額・減額に合理的理由がなく定期同額要件を外れた
法人税・資金繰りへの影響
-
損金不算入により法人税が増加
-
役員報酬が資金繰りに直結するため、適正額設定を誤ると納税資金を圧迫
-
金融機関は役員報酬水準を経営者の生活費・返済能力の指標として重視
実務アドバイス:今日から始めるステップ
-
期首3か月以内に報酬額を決定する
株主総会議事録や取締役会議事録で正式に決議し、根拠を残す。 -
業績予測を踏まえた適正額を設定する
法人税・社会保険料・生活資金のバランスを試算する。 -
途中変更は極力避ける
不可避な場合は「著しい業績悪化」など合理的理由を整え、証拠資料を残す。
注意すべきポイント
-
税務署は形式より実態を重視する
議事録の形式だけ整えても、実態が伴わなければ否認される。 -
社会保険料負担にも直結する
報酬を高く設定すれば法人税は減るが、社会保険料負担は増える。総合判断が必要。 -
金融機関対応を軽視しない
役員報酬が極端に低いと、経営者の生活費不足を疑われ、融資評価に悪影響。
まとめ
役員報酬は「期首3か月以内に決定・同額で支給」が鉄則である。
安易な途中変更は損金不算入リスクを招く。
税務・社会保険・資金繰りを見据えた適正額設定が、法人経営を守る。
出典
-
国税庁「役員給与の損金不算入」
-
国税庁「定期同額給与」
-
国税庁「事前確定届出給与」